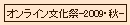我が家の煮っ転がし
我が家には風変わりな居候がいる。そいつの態度はでかい。
春は俺が仕事に出ている日中、風雅に桜を眺めちゃ花見客から「かわいい〜!」と馳走攻めだったとふんぞり返って自慢し。
秋は残業を終えて帰ってきた大黒柱に対し、芸術の秋だと優雅に『ぢゃず』を聴きながら酒を舐めては開口一番肴をよこせとくる。
さらに態度だけでなく、そいつは体もでかい。
デブだ。
標準的なデブを軽く二回る。いや、二・五回る。
それも見た目通りの大食漢で、我が家の食費をキレイに半分持っていく。いや、秋口を過ぎてからは俺の食費まで軽く上回りやがり出した。
今朝ともなると、なんとまぁマツタケを所望してくれた。もちろん国産だ。昨夜は残業と付き合い飲みのコンボで遅かったから、ゆっくり昼近くまで寝ようとしていたせっかくの休日――土曜の陽も昇らぬうちから俺を叩き起こしてくれると、奴は悪いことをしたなんて顔の一つもなくそれどころか至極当然とばかりに形も太さ大きさも指定し作る料理も当然指定してきて必要数計七本なり。そうして追い出されるように一般人にも開放されている市場まで行かされて、指定された通りに八百屋に窺うと、なんとまぁ仰天することに「一本あたり一諭吉と惜別する覚悟」を求められた。もちろんキャンセルだ。そんなものは買えない、買えるわけがない。あの妖怪め、給料日まであと二週間もある上に来月の食費にまで手を出させて……俺を飢え死にさせるつもりか!
もちろん奴は抗議してくるだろう。
脅し文句を並べて購入を迫るだろう。ひょっとしたら今夜は文字通り悪夢を見るかもしれない。
だが、もちろん!
俺は今回ばかりは譲るつもりはない。断固拒否する。何だったら二・三日、駅前のビジネスホテルで寝泊りしてもいい。なぜならそっちの方が断然安上がりだからだ。
意を決し、でもちょっと気後れして近所のファストフード店でコーヒーを飲んで間合いを取って、もう一度覚悟を固めてから帰宅すると、俺は玄関を開けると同時に決意を表明しようとしていた声を失い代わって口からため息を吐き出した。
――サキチは、出かけていた。
あのデブ猫ときたら……そうだ、いつもそうなんだ。いっつもこうなんだ。人間様の心を見透かしたかのように、今日で言うなら人が並々ならぬ覚悟をしてきた時に限って姿を消してくれる。加えて、文句を言おうとしようものなら機先を制してしゃがれ声を挟み込んで意気を奪いにくるし、文句を言われたとしてもいけしゃあしゃあとした物言いで丸め込んでくる。
「はぁ」
ため息が出る。
情けないと言わば言え、そうだ、俺はいつも猫の手の上で踊らされている。いっつも負かされている。だからこそ、どうせ情けないのならと家出をする覚悟までしていたというのに……もう夜だ。マツタケを頼んだくせに食事時を過ぎてもヤツは帰ってこない。つけっぱなしのテレビからは9時台のニュースが流れている。そこではアナウンサーが今朝方首都高速で起きた玉突き事故について語っていた。
駅前のビジネスホテルにキャンセルの電話を入れた時にはさすがに涙が滲んだものだ。
食事も外でするつもりだったから料理をする気もおきず、腹に収めたインスタントラーメンの塩気はいつにも増してきつく感じられたさ。
「……はぁ」
「何をため息なんぞついている」
しゃがれ声が、ふいに、冷め切って表面の脂が白み出したインスタントラーメンの器を片付けようと立ち上がった俺の足下から駆け上ってくる。
「マツタケはどうした」
いつの間にか――玄関のドアを開ける音も閉める音もなく部屋に入ってきていたデブ猫は、その小汚い茶色の毛皮で包んだ太く丸い体躯からは想像もつかない軽やかさでテーブルの上に飛び乗ると、俺が手にしようとしていた器を機嫌悪そうに一瞥してから言った。
「値に、尻込みしたな」
「ぐぅ」
ぐうの音も出ない――という常套句は、嘘だ。
こんな時に出る音は“ぐう”の他にあるもんか。この化け猫め……ッ!
「ま、ちょうど良い」
「……何?」
「ちょうど良かったと言っている。マツタケは、いらん」
サキチは意外なことを言うと面倒臭そうな様子で尻尾を一振りした。その一振りはまるで『この話題はもういい』と示しているようだった。
……その態度に何だか腹立ちを覚えながらも、半面マツタケの件で口論をして――そもそも論戦自体がなくなったことで“負ける”ことがなくなったことに――安堵している自分がまた、情けない。
「何をしょぼくれている、ヨシユキ」
「うるさいな。しょぼくれてなんかない」
「嘘をつくな」
「嘘なもんか」
「変な意地は恥を増すだけだぞ。客も笑っている」
テーブルの上に姿だけは猫らしく座る小汚い茶色は、至極真面目な顔をして言う。
「……なんだって? 客?」
俺の住むこのマンションの一室に、俺とサキチの他には誰もいない。いや、正確には、サキチに脅かされて身を縮めている悪霊が部屋の隅にでもいるはずだけど、その他には誰もいない。
俺が聞き返すと、サキチはまた面倒臭そうに尻尾を一振りした。
「勘の悪い奴め。お前に見えぬ客ならば……決まっているだろう?」
ざっと、自分の顔から血の気が失せる音が聞こえるようだった。
「そうだよ、ヨシユキ。ほれ、彼女はお前の背後にいる」
ぎゃー! と悲鳴を上げた後、そう言われたところで結局振り返った先には何も見えず、見えないなら恐れることはないかと気を取り直した俺は、何を考えているのか「里芋を買って来い」とサキチに言われて訳も分からぬまま近所のスーパーへと自転車を走らせた。
しかし――
思い返せば、化け猫と同居している俺が今更幽霊ごときを恐れることはないのではなかろうか。
なにせ一度は悪霊に取り殺されそうになった身でもある。それを考えれば、やっぱり「何を今更、幽霊ごとき恐るるに足らず」なんて言い切ってもいいくらいのレベルじゃないか? 俺。
――と、そう思い至ってからは心も平静そのものに、しかしそう思い至ると同時に悲鳴を上げた自分が恥ずかしくてたまらなくなるもので。化け猫の、悲鳴を上げた俺を見るあの人を食った顔つきをも思い出すと、悔しいやら情けないやらでなおさらいたたまれなくなる。
ポップに今が旬だと書かれていた里芋の大袋を入れたエコバッグを片手に帰ってきた俺は、もうサキチに馬鹿にされてはやるもんかと、悲鳴を上げた自分を打ち消すように自信満々の顔で玄関を開け、
「ぎゃー!」
悲鳴を上げた俺を眺めるサキチの目は、実に底意地悪く細められていた。
そして今、俺は、宙に浮かぶうっすら透けたおばちゃんの指導の下で、里芋の煮っ転がしを作るはめに陥っている。
「……なあ、サキチ、そろそろ事情を説明してくれてもいいんじゃないか?」
幽霊のおばちゃんは、まさに“おばちゃん”と言った風体で。小太りの胴の上にころりと丸い頭を乗せ、緩いパーマのかかった短髪の下にそこそこ人の良さそうな笑顔を浮かべている。服はシャツの上に地味な色のカーディガン、それにコットンパンツ。どこか近所の店に買い物に行く、くらいの格好を思わせる。年の頃は五十代。子育てを終えた貫禄が滲んでいる。もしかしたら、うちの母と同い年かもしれない。
おもしろいのは足がないことだ。実に幽霊らしい。いや、おもしろいと言っては失礼だろうけど、お陰で彼女が本当に幽霊なのだと思うことができる。
「成仏できないそうだ」
サキチは相変わらずテーブルの上にいて、今は四肢を伸ばしてだらしなく寝転がっている。ドでっかい毛虫みたいだ。丸々肥えてるものだから、怪鳥が見たらきっとヨダレを垂らすだろう。
「それぐらい解る。お前、迷える霊を成仏させるボランティアまでやってたのか?」
「していない。こんな面倒なこと頼まれてもやらん。それに、そもそも滅多にいないからな」
「滅多にいない? 何が?」
「お前達が幽霊と呼ぶものが、だ。ここ五十年で見かけたのは片手で足りるな」
「そうなのか? うちには悪霊がいるぞ?」
「運が悪かったな。人に仇なすものは五十年に一度見るかどうかだ。いや、これは運が良かったと言ってやった方がいいか?」
「余計なお世話だ。それに霊関係の話は世間じゃ結構頻繁に聞くもんだけどな?」
「ああ、そうだな」
のん気な肯定を受けて一度里芋の皮を剥く手を止めて振り返ると、サキチはあくびをしていた。
「そんなに霊が見える人間がいるなら、吾が輩は今頃見世物小屋のスタァだろうな」
「それは、妙にコメントに困る言い方だな」
「そうか? だが、だから、そういうことさ」
続けて、“だから”その手の商売には引っかかるなよ、お前は引っかかりやすそうだからな。と、サキチはニーッと思わせぶりな笑みを見せる。
俺はさらにコメントに困り、変な形の笑顔だけを返すと作業に戻った。ひとまず買ってきた里芋の全ての皮を剥き終えて、さて、と隣でふわふわ浮いているおばちゃんに声をかける。
「それで、次は?」
「そうなのよねぇ。松島さんったら、あんなに霊感があるんだって言ってたのに、私のことにちっとも気づいてくれないんだから」
声が、頭に直接響くようにして聞こえてくる。初めはこそばゆいような感覚を覚えたけれど、今ではもう慣れた。
「……え?」
「やぁねぇ、幽霊が見える見えないの話よっ。お兄さん若いのにもうボケが始まっちゃってるの?」
わりあい早口に、ちょっと人を攻めるような口ぶりで、けれどまぁ悪気は皆無の調子でおばちゃんは言う。それにしても、死んでいて、さらに成仏できないでいるというわりにはやけに明るい幽霊だ。
「そりゃあめったにお化けが見える、なんてことは言わなかったけどね? 松島さんたらあの有名な占い師は詐欺師だ、こっちの雑誌の人が本物だ、なんて自信満々に言ってたのに」
「いや、そうじゃなくて。次はどうすればいいんです?」
「え? あ、ああ! あらやだ、そうね、お仕事頼んでるのに勝手に話を進めちゃってごめんなさいねぇ?」
この際それはいいのだけれども。困惑する俺をよそにおばちゃんは、これだからおばちゃんはうるさいとか言われちゃうのよね、とかまた話を一人進めている。
こうして俺が“おばちゃん”を見て、声を聞くことができるのは言うまでもなくサキチの仕業だ。妖術か魔術か超能力かは知らないしそれを使う姿を見せてもらったこともないが、しかしこの事実は、改めてサキチがただ人語を理解するただの怠惰なデブ猫ではないと再認識させてくれる。実際不思議なので、本音を言えば一度妖術だか何だかを使う瞬間を見せてもらいたいと思うのだけれど――だけれども、今はそんなこと、どうでもいい。
「お父さんからも言われてたのよぉ。お前は人の話を聞かないって。そんなことないって言ってたんだけど、やっぱりそうだったのねぇ。お父さんの言うこと、もっと聞いてあげればよかったわぁ」
「はぁ、そうですか」
何となく、サキチが面倒臭そうにしていた理由が分かった気がする。俺にマツタケを要望しながら、帰宅が夕飯時を過ぎていた理由も。
それに、だ。『こんな面倒なこと頼まれてもやらん』と言っていたくせにサキチがおばちゃんの成仏を手伝おうとしているのは、むしろ頼むから成仏してくれとでも思ったからなんだろう。きっと間違いない。それでなぜに俺が里芋の煮っ転がしを作るはめになっているのかは、まだ解らないにしても。
「あらま! また一人で勝手にペラペラしゃべっちゃって、ごめんなさい?」
「……いえ、いいんですけども、えっと」
「塩で揉め」
闖入してきたのはサキチのしゃがれ声だった。だらしなく寝転んでいた姿はどこへやら、どうやらおばちゃんのペースに我慢が出来なくなったらしい。眉間に皺を寄せた顔で立ち上がると、台所の脇にある電子レンジの上に移動する。そこは、サキチが俺に料理の指導をする時の定位置だ。
「ぬめりを取れ」
確かに、前に煮っ転がしを作った時、サキチはそう言っていた。料理本にもそう載っていたはずだ。
「あらあら、そんな面倒なことっ」
が、それを笑顔でおばちゃんは否定した。
「そのまま鍋に入れて、水を入れて?」
サキチは――何かを言いたそうに首をもたげていたが、本当に何を考えているのか、気を紛らわせるように後ろ脚で(いい加減腹につっかかって届かなくなりそうなのに驚異的な柔軟性で)耳をかくとそのまま黙り込んだ。レンジの上からごろごろと里芋を入れた鍋に水を……おばちゃんに言われるまま、やけに多くの水を注ぐ俺の手元をしかめっ面で見つめてくる。
「ダシはある? 袋で売ってるの」
「袋で?」
カツオ節なり顆粒なり、大抵のダシの素は袋に入って売られているものだけど……。
「そう袋。ほら、あれよあれ」
「あれと言われても」
「ほらー、あれ、紅茶の」
「紅茶の? ああ、ティーパックタイプ」
「そう! それ!」
要領の悪いやり取りに、なぜか苛立ちよりも笑いが込み上げてくる。何となく、うちの母とのやり取りを思い出す。
俺は――サキチは好かぬとそっぽを向くが、手軽さを重宝して常備しているパック式のダシを取り出し、別の鍋を取り出して
「あら、何をしてるの?」
「え? だってダシを取るんじゃ……」
「もちろん取るわよ? ほら、だからそれはそっちに入れるのよ」
おばちゃんが指差したのは、里芋が並ぶ鍋。
「……下茹では、しないので?」
「あらあらそんな面倒なことはしなくていいのっ。手際良くさっさとやるのよっこういうものは」
「はぁ、そうですか」
とにかくおばちゃんの言うとおりに俺はダシパックを指定の鍋に放り込んだ。火を点ける。以前、サキチは先にダシを取っておいて、それと下茹でした実を合わせるように言っていたし、料理の手順を省くのが手際の良さなのかどうかは甚だ疑問に感じるけれど、まあこれはこれで“あり”なやり方なのだろう。
「それじゃ、お酒とみりんと砂糖とお醤油、入れましょう」
「え?」
「何?」
俺の疑問符に続いて、思わずといったようにサキチも疑問符を打った。四つの瞳が向けられた先でおばちゃんは、何か変なことを言ったかしら、とばかりにきょとんとしている。
「早く……ないですかね?」
火にかけられた鍋はまだ静かなもので、煮立つ気配はまるでない。当然ダシも少しも出ていない。このタイミングで、味付け?
「一気にやったほうが楽じゃない。煮込んでいる間に他のものに取りかかれるし、うちはおばあちゃんの代からこのやり方よ?」
おばちゃんのおばあちゃんがメインで食事を作っていた時代にパック式のダシがあったかどうかは分からないが、おそらく似たようなやり方ではあったのだろう。
「それがお前の家の味か」
「そうそう、猫ちゃん。その通り」
猫ちゃん呼ばわりされたおばちゃんよりもずっと年上の化け猫様は閉口したように後ろ脚で耳をかくと、ひとまず役目は終えたとばかりにレンジの上から飛び降りリビングに向かっていった。先月俺用に買ってきたのにいつの間にかサキチの指定席になっていた座椅子に辿り着くと、まるで不貞寝をするように丸くなる。
正直、サキチが羨ましかった。
少々疑問を覚える分量・比率の調味料を言われるまま目分量で入れた後、落し蓋もせず中火で里芋を煮込んでいく間、ずっとおばちゃんの世間話に付き合わされるのはもちろん俺だ。
ダイエットの失敗談だの金木犀の香りが好きだの交友関係の愚痴だの孫が可愛くてしかたないだのとりとめのない上にマシンガントークという常套句が素晴らしく当てはまるおばちゃんの会話にそろそろ撃ち殺されそうになった頃、天の助けのようなタイミングで里芋の煮っ転がしが出来上がってくれた。
「味見は……どうするんだ?」
化け猫は肥えた舌で美味いの不味いの講釈を垂れるが、さすがに幽霊がそうすることはできないだろう。煮汁の少なくなった鍋をゆすって芋を転がし仕上げ終え、そう思って座椅子で丸まる――寝ていやがった!――サキチに問うと、意外な方向から答えが返ってきた。
「味見なんて面倒なことしないわよ。完璧よ、完璧」
「それで……大丈夫なのです?」
「大丈夫よ、いつもそうだもの。だって見た目は完璧よ? なら味も完璧じゃない」
明らかに破綻しているはずの論理もおばちゃんに自信満々に断言されると正しいような気がするのは幽霊に料理を習っている現状以上に不可思議なものだ。
確かにうちの母も急ぎの時には味見をせずに作って、それでちゃんとしたものを出してきていたから、これはベテラン主婦の特殊技能というやつなのかもしれない。
「あ、だけど食べてみて? 反応を見たいから」
「はあ、それじゃあお言葉に甘えて味を見させてもらいますけど……」
「吾が輩ももらおう」
いつの間にか台所に戻ってきていたサキチが自ら進んで言ってくる。どうやら、おばちゃんの作り方でどのような味になるのか興味はあったらしい。
果たしておばちゃん指導の下で作り上げた煮っ転がしは、煮加減はちょっと外側がふやけすぎてる気がするものの許容範囲、が、色はひどく濃い仕上がりだった。早くから醤油で――それも他の調味料に比べて明らかに多く入れた醤油で染め上げたために、煮物に求める色合いよりずっと黒い。ぬめりを取らなかったためか里芋特有の粘っこさが強く主張され、そこに味が良く染みすぎているような様は実に不安を掻き立てる。鍋から取り出し皿に乗せた里芋一つ、菜ばしで二つに割り、片方を皿ごとテーブルの上のサキチに差し出し、おそるおそる、残った片方を口に運んでみる。
「……」
驚くべき味だった。
何と言えばいいのか、これは絶妙な加減で……そう、いまいちだ。
正直、外縁は味が濃すぎる。色のイメージそのものに醤油の味が勝ちすぎ、香りはなんと最後まで取り出さずに入れっぱなしだったダシパックの煮出されすぎた臭いが里芋の香味を消している。けれど反対に、どうしたことか内側には味が染みていない。とはいえ味が染み込んでいなくとも、いや、この場合味が染み込んでいないからこそか? 旬の食材らしく香りも味も素晴らしく、外縁に比べて内はそれなりの煮加減になっていて食感も悪くない。
……だから……本当に、摩訶不思議なことだけど……この煮っ転がしは、外と内が合わさると何となく味のバランスが調うように出来ていた。
この味のバランスの悪さ――いや、むしろバランスの良さはお見事の一言に尽きる。
おそらく、これらのどの要素が欠けても、この味は成り立たないだろう。
おかしな言い方だが、
「芸術的にイマイチだ」
サキチが率直に言った。全く同意見だった。
おばちゃんの眉が垂れる。あからさまにしょぼんと肩が落ちる。
こうなると成仏どころではあるまい、これはまずいと思って何かフォローの言葉を探していると、おばちゃんは透けた体をさらに透き通らせるようにため息をついた。
「やっぱり、あなた達もいまいちだと思うのねぇ」
「……やっぱり?」
「おいしいと思うのよ? わたしは。でも家族にはずっと不評だったのよ。いまいちだ、って。でもこれがわたしの家の味だから直さないできたんだけどね? だってね? おばあちゃんも、お母さんも、秋になると里芋をたくさんもらってきて、これを作ってくれて、わたしが美味しいって言うと喜んでくれたから。わたしも一度でもそう言われたくってねえ。意地になってたのもあるんだけろうけど、今思うと少しは本の通りに作ってあげれば良かったかしらねぇ」
片の頬に手を当てて言うおばちゃんは、悲しいと言うよりも、ただ残念という顔をしていた。
「だが、そのおかげで助かった」
すると何のつもりだか、サキチがそう言った。おばちゃんはサキチの言葉にちょっと思案顔を見せた後、そうねと頷いた。
俺は話が飲み込めず戸惑うばかりだったが、もう俺の役目が終わったことだけは理解できた。後は、
「ヨシユキ、冷めたらタッパぁに詰めてくれ」
「俺はついていかなくていいのか?」
「いらぬよ」
「いや、だって誰が持っていくんだ」
「風呂敷にでも包んでくれ。吾が輩が持っていく」
「どうやって」
「吾が輩の尻尾はお前の手より器用さ」
「人目に立つぞ」
「目立たぬよ。何しろ目立たぬようにできるからな」
「……化け猫め」
「化け猫様だ。帰りは明日の晩になるだろう」
「分かった。酒と肴は用意しておくよ。マツタケは駄目だが」
特に“マツタケは”に力を込めて言うと、ふいにおばちゃんがマツタケは高いものねぇと相槌を打つ。これは予想外の助勢だった。もし、サキチが抗議をしてきても、もしかしたらこの成仏できずにいる幽霊の力を借りて……初めて、初めて勝てるかもしれない。
そんな期待を胸にサキチの返答を待っていると、化け猫はこちらの意図せぬ笑みをニーッと浮かべ、
「役に立った褒美だ。譲歩してやろう」
こ、このデブ猫、なんとまあ偉そうに目線も大上段から言い返してきやがった!
「代わりに旬の肴を用意しておいてくれたまえよ、ヨシユキくん」
老獪な妖怪を負かす千載一遇のチャンスだったと思うのに……嗚呼。
「ヨシユキくん?」
「あー、分かりましたよチクショウ」
「畜生ではないな」
「あー、はいはい。分かりましたよ、この化け猫様が」
*******
杉山ミツコが死んだのは、およそ半年前の雨の日だった。
享年54。死因は主に頭部外傷。原因は、自らが起こした事故。赤信号を無視して交差点に侵入後、右方より同交差点に青信号を直進してきたトラックと衝突、全身を強く打ち、病院に運ばれた後、そのまま帰らぬ人となった。
目撃者によると交差点侵入前に杉山ミツコは運転席内で慌てた様子を見せ、ハンドルの下に手を伸ばす素振りを見せていたという。その後の調査で、杉山ミツコは買い物袋からこぼれて足下に転がってきたものを拾おうとして赤信号を見落とし、そのため運転を誤ったと推察された。
そして、それは実際、正しかった。
無論、それが真実正しいと明確に知るのは、故人である杉山ミツコただ一人である。足下に転がっていたものが缶ビールであったことを知るのも、彼女一人だ。床には事故の衝撃で助手席に置かれていたらしい買い物袋から飛び出した品々が散らばっており、そのどれが初老の主婦を死に導いたのかと確実に特定できる者はなかった。
そう、確実に特定できる者はなかった。
だが、確実にでなければ“特定”は誰にでも出来ることでもあった。
杉山ミツコの夫、タダシはこう結論付けた。ミツコは、缶ビールを拾おうとして死んだのだ。
夫の結論が当たっていたのは、ただの偶然だった。しかしその偶然を導く理由は、確固たるものとして彼の中にあった。
――その日の朝、杉山夫妻は大喧嘩をしていた。
喧嘩のキッカケは、タダシがミツコの何気ない一言に過剰に反応したことにあった。杉山夫妻はよく喧嘩をする夫婦であり、喧嘩をすることそれ自体は珍しいことではない。しかし、いつもと違ったのは、いつもは多少喧嘩をしたところで出勤する時になれば夫を必ず見送り続けてきていた妻が、その日の朝は台所に引っ込んだまま夫を見送らなかったほどの大喧嘩だったということ。その日の喧嘩は夫妻にとって、何十年ぶりかという格別の大喧嘩であった。
杉山夫妻には、約束事があった。
例えどれほど喧嘩をしようとも、その日の晩には仲直りをしよう。怒りは翌日に持ち越さない。二人で一緒にビールを飲んで、水に流そう。
普段、杉山ミツコは酒を飲まない。杉山タダシは普段は焼酎を飲み、ビールを飲まない。だが、その日、ミツコの運転する車には、缶ビールが二缶あった。他に床を転がり――例えばブレーキペダルに挟まりそうだとミツコを慌てさせるようなものはいくつかあったが、しかし、タダシはそれこそが缶ビールだったのだという強い確信を持っていた。
だから、タダシは言った。
俺があいつを殺したんだ。
杉山タダシは涙を流さなかった。流す暇がなかった。冷たくなった妻と対面した時も、もっと先で、もっと安らかなものだと思っていたはずの母の死に直面した我が子らの悲鳴と嗚咽を聞いた時も。ただ涙をこぼす代わりとでも言うように、彼は、申し訳ない、申し訳ないと言い続けた。手を尽くしてくれた医者に、事故の報をくれた警察に、青信号を直進していたとしても過失を問われた事故の相手に。申し訳ない、申し訳ないと頭を下げ続けた。突然の悲報に、通夜に、告別式に駆けつけてくれた親戚縁者に、死んだ妻の友人知人たち、また家族の友人知人たちに――申し訳ない、申し訳ない。
骨になる妻を見送った時も、骨になった妻を前にしても、葬儀一連の事柄を終え、雑事がなくなり落ち着いた頃に一人分の存在が消えて急に広くなった家に一人残されることになったと実感した時でさえ、タダシの双眸からこぼれるものはなかった。
心が行き場を見失い、ただ、悔恨のため息だけがあった。
あの日、喧嘩をしなければ。
あの日、玄関に出てこない妻に俺がビールを買ってくると言えば。
悪かったのは俺だ。俺がつまらない言いがかりをしなければ。
……ミツコを殺したのは、俺なんだ。
その言葉を聞いた誰もが、そんなことはないと彼を慰める。お父さんは悪くないと、夫妻の独立した息子と二人の娘も言う。幼いながらに何かを感じ取ったのだろう、おじいは悪くないよと小さな孫娘も言う。
しかし、誰の言葉も、力を失い落ちた彼の両肩を持ち上げることはできなかった。
タダシにとってはつまらないドラマの、つまらないコメディシーンに甲高い笑い声を上げるミツコのない家は寒く、外気には秋風が吹けども、内にはすでに真冬の風が通り抜けている。
その日の晩、温かいはずなのに薄ら寒い毛布の中――タダシは夢を見た。
何度も見る夢だった。
国道を直進していく紺色の軽自動車。昨年買い換えたばかりで、それまで十年乗り込んできた車に比べて静かだの燃費がいいだのスピーカーの音が全然違うだの、分かったようなことを妻は言っていた。流行の音楽は解らないと言いながら、気の早いことに、幼稚園に通う孫娘が年頃になった時に話題についていけるようにとヒットチャート上位の曲をレンタルしてきてはかけ流し、たまにアイドルのアップテンポな曲に調子っぱずれな鼻歌をあわせて同乗している夫を辟易させていた。
タダシは紺色の軽自動車を歩道から眺めている。運転席には妻がいる。だが、顔は見えない。下の娘にダサいから新しい美容院に行きなよと言われながら、馴染みの年寄りが集まる美容院でつくろった髪だけが見える。
タダシは叫んだ。
赤だ!
軽自動車は進んでいく。真っ直ぐ、道を進んでいく。
ブレーキ! ブレーキ! おい、赤だ! 赤だぞ!
タダシは必死に叫ぶが、車は止まらない。周囲にはアイドルの曲が大きく響く、彼の声を消し去るように。
悪かった! 俺が間違っていた! だから止まってくれ、ミツコ!
タダシは悲鳴を上げた。
赤信号を無視して交差点に入っていった小さな車に、同時に交差点に入ってきた大きな車が迫る。妻のいる運転席が、恨めしくもタイミング良く、減速する必要も――その暇もなく青信号を直進してきたトラックに……潰される。
音はなかった。
何の音もなくなっていた。
衝突音も、妻の悲鳴もない。せめて、妻の悲鳴だけでも聞こえればよかった。いや、聞かねばならなかった。
タダシは霊安室に置かれた妻の死体を前に茫然と突き立ち、つぶやいた。
俺が殺したんだ。
「そんなわけがないじゃない!」
その時、ベッドに静かに横たわっていた死体が勢いよく体を起こし、怒鳴った。怒鳴られたタダシは驚きのあまり腰を抜かすことも出来ず呆然と突っ立ったまま、見慣れた猫のアップリケがついたエプロン姿のミツコを見つめていた。
「わたしがお父さんに殺されるなんて、そんなことがあるわけないじゃないの」
タダシはリビングにいた。いつの間にかイスに座っていて、目の前のテーブルには食べかけの目玉焼きがあり、リビングから見える台所に、妻がいた。腰に手を当て、仁王立ちで。彼女の前にはことことと音を立てる小鍋がある。醤油の匂いと、覚えのある食物の匂い。
ああ、と、タダシは理解した。
ここは、事故のあった日の朝だ。これは夢なのだから、時間が巻き戻ってもおかしいことなんてない。
「なんでそんなひどいことを言うの」
あの日と同じように顔に怒りを滲ませる妻は、しかし、あの日とは違い悲しそうに言う。どうやら巻き戻っているのは時間だけで、妻は自分が死んだことを理解しているらしい。彼女の脇でコンロにかけられた鍋が湯気を立てている。煮込まれているのは里芋の煮っ転がしだ。特に里芋が旬だと売り出される秋になると妻が必ず作る品、あれは味が良くないから好きじゃない。葬式だ何だと慌しく、あの鍋の中のものは結局悪くしてしまった。捨てる時、食べておけば良かったと激しく後悔した。
「ねぇ、お父さん。わたしはお父さんのせいなんかで死んだんじゃない。全部、わたしのせいでしょう?」
「いや、いやだが、俺が……」
タダシはようやく妻に声を返し、すぐに言葉に詰まった。
夢だと理解しながらも、不思議なことに目の前にいる妻を“夢の中の妻”だとは思えない。本物の妻の――信じられないことだが――幽霊を前にしているようで、妙に気後れしてしまう。悔恨と懺悔の念から、口が粘ついてうまく動かない。
「……お前は、お前は、ビールを……」
「そう、ビールを買っていた。それで?」
「転がったんだろう? お前はそれを拾おうとして」
「あたりよ、お父さんったら変なところで勘が働くんだからもう」
「だったら――」
「だったら、何? これがジュースだったらどう? リンゴだったら? タマネギだったら? 全然別のものだったら? お父さんのことだからどうせ『俺が買い物に行っておけば』とか言い出すんでしょう。違うわ、全然違う。わたしのせいよ。わたしが注意不足だったの。エコバッグを忘れちゃってスーパーの有料のを買うのがもったいなくて一枚だけ買って、一つの袋に目一杯詰めすぎちゃたのが失敗、ケチらずもう一枚買ってちゃんと分けなおせば良かった、袋をちゃんと置いてなかったのも失敗、崩れそうになっていることは分かってたのに横着して直さなかったのも失敗、ビールが足下に転がってきたのは運が悪かったけど、それだって慌てず止まってから拾えば良かった。どう? これでもお父さんのせい? どこがお父さんのせい? わたしの行動は全部お父さんのせいでなけりゃいけないのかしらね? ひょっとしたらスーパーの袋が有料になったのもお父さんのせいなのかしら。だって有料じゃなかったらわたしはちゃんと二つに袋詰めして死んでなかったかも」
どこで息を継いでいるのか分からぬほどの速度で畳みかけられ、タダシはぐうの音も出ず押し黙った。
いつもこうだ。ミツコと言い合うと、このマシンガンに攻められる。だからこちらは負けずと怒鳴り声の大きさを上げ、それが気に食わないとミツコは弾数を増やして一斉掃射、そうしてさらにこちらが声を張り上げる悪循環。
「――分かった。分かった、悪かった。俺が間違っていた」
タダシは、笑いをこらえるようにして、言った。
あの朝の悪循環は極悪だった。ついには声を張り上げられる限界を超えた自分にできたことは、テーブルを殴りつけて食事を残して会社に行くこと。妻は、必ず行っていた見送りをしなかった。
「俺のせいじゃない。分かったよ」
再び、あの朝をくり返すことはない。こうやって、間違っていた自分が折れてやればよかったのだ。
「まったく……馬鹿者が。どれだけの人に迷惑をかけたと思っている。相手の方にとんでもない思いまでさせて」
夫の言葉に、ミツコは――唇を小さくすぼめた。それだけで、タダシは妻がどれだけ悔いているのか理解した。呆れるほどのおしゃべりなくせして、言葉を見つけられない時には妻はああやって口をつぐむのだ。その顔は哀れにも滑稽にも見えて……今は、悲しく見えた。
「それに、それにな、早すぎるだろう。本当に、馬鹿者が」
「ごめんなさい」
「……謝るな」
「そうね。どうせお父さんもいつかこっちにくるんだしね」
一転、ミツコはケロッとして言った。そのあまりの変わり身にタダシは一瞬呆れ、思わず癇癪を起こしそうになり、しかし気を取り直して言い返した。
「何を言うか。俺はそっちには当分いかん。まだこっちでやりたいこともある。定年したら旅行に行きまくるんだ。覚えているか、お前が行きたがっていたパリにだって行く。ミツタカにもヨシコにもケイコにも迷惑かけるジジイになって、孫を思いっきり甘やかして、お前とするはずだったことを存分に楽しんで……お前を悔しがらせてやるんだ、どうだ、ざまあみろ」
「そうね。そうね、お父さん。悔しがらせてみなさいな」
ミツコは微笑み、タダシはぐっと口をへの字に曲げた。
「そうだ、お父さん。わたしのへそくりは見つけた?」
「へそくり?」
「物置にケイコの勉強机があるでしょう? あれの引き出しに80万円入っているわ」
「80……っ!?」
「大変だったのよぉ、コツコツコツコツ、100万貯まったら一気にパーっと使うつもりでね?」
「お、お前なぁ」
タダシが心底呆れた顔をすると、ミツコは笑った。そんなわけがないじゃない、と。老後のもしもの時のため、と。
「それから、これから言うことをちゃんと聞いておいてね。どこに何がしまってあるか、どういう時どうすればいいのか」
「そんなことを気にして出てきたのか? お前はもうそんな心配しなくていい。ゆっくりしていればいいんだ」
「あら、そんなこと言って。これから必要になる湯たんぽがどこにあるかも知らないくせに」
図星を突かれ、タダシは黙する他なかった。それを見たミツコはほらやっぱりと笑い、妻の目尻が作る皺に、それだけ年数を数えてきたんだなと夫は思った。
それからミツコはタダシにいつもの調子のマシンガントークで必要事項を伝えた。一度では不安だからと、二回言った。さすがに二度目ともなると時折脱線するミツコのしゃべりにタダシは辟易とするものがあったが、最後に「さて」と結ばれた時には、ぐっと心を締めつけられ顔を曇らせた。
「待て、もう少し……そうだ、ミツコ、一緒にビールを飲もうじゃないか」
「どこにあるの、そんなもの」
「ある! ここは俺の夢の中だ。そうなんだろう? だったらビールなんてほら、冷蔵庫を開ければ――」
ミツコの脇をすり抜け冷蔵庫の扉を勢いよく開こうとして、タダシは「あ」と声を上げた。彼の手は、冷蔵庫の取っ手を掴むことがなかったのだ。何度掴もうとしても、手は取っ手をすり抜ける。まるでそこにあるように見える立体画を相手にしているようだ。
「夢ね。半分、あたり」
「半分?」
タダシは妻の言葉に、眉根を寄せた。
「親切な……ヒト、がね、お父さんに会わせてくれるって。実はね、情けないんだけど、立派なお葬式まで出してもらっておきながら成仏できないでいてね、実は今までさまよっていたの。また迷惑かけちゃったわ。わたしはホント、だめねぇ」
「そんなことはない!」
「え?」
「だめなんかじゃあない、お前は……」
そこまで言って、タダシはうつむいた。握られた拳は震え、肩は……妻が死んでからというもの落ち込んでいた肩は、怒るように持ち上げられている。
「お父さん。いつも言っていたことだけど、帰ってきたら家の鍵はちゃんと閉めてね? 開け放しは無用心だから。そして――元気でね?」
タダシは、顔を上げた。
そこにはもう、ミツコの姿はなかった。
「待て!」
と、そう叫んだ自分の声で、タダシは目を醒ました。瞼の向こうにはまだ夜があった。カチ、カチ――と秒針の音が部屋に鳴り、どこからか虫の音が聞こえてくる静かな夜だった。
何だ、夢か。タダシは思った。妻との再会、会話、そして再びの、本当の別れと同じにあまりにあっけない別れ……そういう夢。
いつもの悪夢に疲れたのだろう、あれは逃避の夢だ。
そう思うと、口元には自然と笑みが浮かんでくる。苦笑ではない。情けないと、自嘲する笑みが。
タダシはため息をつき、床を出た。そういえば玄関の鍵をかけ忘れていたことを思い出したのだ。死んだ妻に夢で言われてやっと気づくなど本当に情けない――と閉められた仏壇を見て、また笑う。
寝床としている床の間から玄関に通じる廊下に足を踏み出すと、ギシリと音が鳴った。ここだけ踏むと音が鳴る。鳴り出したのは、この家を建ててから三年も過ぎた頃だったろうか。ミツコはその頃からずっと、この音が嫌だと時折思い出したように言っていた。
玄関の鍵を閉めた後、タダシは水を飲もうと台所に向かった。廊下を戻り、音の鳴る箇所を避けて通ってリビングに入った時……ふと、彼はテーブルの真ん中に見慣れぬものがあることに気がついた。
電気を点けて見ると、それはタッパーだった。透明な側面に、中にある何か色濃い物が透けて見える。
タダシは置いた覚えのないものがそこにあることを不気味に思うよりも先に、己の血が粟立つ音を聞いた。まるで失念していたとても大事な約束をふいに思い出したかのように、ぞっと心臓が締めつけられた。
タダシはテーブルに駆け寄った。
タッパーを手に取り薄青の蓋を引き千切らんばかりにはぎとると、やはり、そこには予感した通りのものがあった。
「――ミツコ!」
タダシは叫んでいた。
夢の中、妻が最後に遺した言葉を思い出す。
元気でね。
そんな簡単な、別れの言葉。
最期にたった一言。
そうだ、妻はしゃべり出すと止まらないくせに、別れの時には言葉を限る奴だった。震えていた声。全ての感情を込めたかのような言葉、夢ではない、この耳に残っている。そうだ、あれは夢ではないのだ、夢なんかではなかったのだ!
「ミツコ!」
タダシは確かに傍にいたはずの、会いに来てくれていた妻を探して家中を駆け回った。夜闇に沈む家に彼の足音が騒々しく鳴り響き、電気は片端から付けられた。彼は妻の名を呼ぶ。だが、応える者はない。
家の中を何周もして、彼は妻を探した。
だが、いない。
外にも出て庭も外回りも探し回るが、いない。
どこにも妻の姿はない。
最後に床の間に行き、タダシはしっかと手を合わせてから、仏壇を開いた。しかしそこには昨夜、扉を閉じる直前と変わらぬ姿があるばかり。戒名の書かれた位牌が夫をただ見返している。
静かに仏壇を締め直したタダシは、リビングに戻った。
椅子に座り、知らぬ間にテーブルに置かれていたタッパーを見る。
そこにはやけに色の濃い里芋の煮っ転がしが詰められていた。
昨夜は確かに、絶対に、ここにこんなものはなかった。もちろん誰かが置いたのだろう。でも誰が? もちろん、タダシにそれを疑う余地はなかった。
彼は少し形が崩れた里芋を一つ摘むと口に放り込んだ。
“懐かしい味”が、口一杯に広がった。
間違いない。こんなもの、他に作れる者はない。あえて作ろうという者もない。娘達も作れないこの品を作ることができるのは、もうどこにもいない。
この世にはいない。
タダシはため息をついた。
「ああ……やっぱり、いまいちだ」
二つ目を摘み、口に入れる。
「やっぱり、お前の作る煮っ転がしは、いまいちだなぁ」
いまいちだ、いまいちだとくり返しながら三つ目を取り、食べる。
冷めても柔らかい芋の実は、彼の鼻腔に長年連れ添ってきた味を今一度蘇らせる。
「いまいちだ」
四つ目を取る。それは一際大きい。半分齧る。
いつしか涙がぼたりぼたりとテーブルに落ちていた。
「ああ……」
ようやく行き場を見つけた彼の心が次から次へと溢れ出す。鼻水をすすり、残った半分を指ごと放り込むように口に入れ、
「うまい」
声を上げてタダシは泣いた。
*******
我が家の風変わりな居候は、気がつけば部屋の中にいたり、部屋から出ていったりする。いくら巨漢とはいえ猫には重過ぎる玄関をどうにかして開けているのか――それとも通り抜けているのか――解らないけれど、とにかく独りで出入りできる。
それなのに、よく人の手を煩わせてくれるのだ。インターホンを決まった間隔で二度押して、それからトムントムンと、開けろ開けろと肉球でドアをノックする。
「黙って入ってこいよ」
「それが一仕事終えた相手に言うことか」
「俺はお前に仕事帰りに労ってもらった覚えはないぞ?」
「いつもお仕事ごくろうなことだ」
いちいち人を逆なでする言い方をしやがる化け猫は、ふふんと鼻を鳴らして内に入り、開けたドアを支える俺の足下をするりと抜けるとシューズボックス脇に向かい、そこに常備してあるウェットティッシュを爪で器用に引き抜くと丁寧に足の裏を拭き……そこでまたふんふんと鼻を鳴らした。
「金木犀か」
「ああ」
「随分簡単だが生け花とは、ヨシユキにしては風流なことをするな」
「そんなんじゃないよ」
後ろ手に玄関の鍵を閉め、サキチの後を追うように部屋に戻る。サキチはテーブルの上の100円ショップで買ってきた花瓶に挿された金木犀の枝に顔を近づけ、珍しく穏やかな笑みを浮かべていた。
そういえば、あいつはフローラルな香りが好きだったか。
「あのおばちゃんは?」
「成仏したよ」
「そうか。それじゃあ、無事に未練が晴れたんだな」
俺が安堵の息をつくと、サキチはまたふんと鼻を鳴らした。
「未練なく逝ける者はそれこそ滅多にないさ」
「え? でも、成仏したんだろ? それなら未練がなくなったんじゃあ……」
「未練は尽きぬものだ、ヨシユキ。一つなくせば次が出る。もし未練ある者全てが迷うのならば、今頃この世は死で溢れかえっているだろう」
金木犀の香りが心をそよがせるのか、また珍しくサキチは穏やかに言う。一度顔を洗うように顔を撫で、
「あの中年女も後ろ髪引かれる思いのまま、逝ったよ」
「……」
「だが、後ろ髪を引く思いもあれば、背中を押してくれる思いもあるものさ。何も杯に目一杯の酒だけが満足をもたらすものではない……だろう?」
「……何か、今日は妙に饒舌だな」
「今日は月が美しい。月に心浮かれるのは、何も人や狼だけではないのさ」
……いや。
サキチは、何かサキチにとって何か心慰むものを見てきたのだ。
何となくだけど、そう思う。
「おばちゃんは、旦那さんに会えたのか?」
俺は台所に向かいながら聞いてみた。
「ああ」
しゃがれた声が頷きを伝えてくる。
「それじゃあ、感動の別れだったろう」
「そうでもないな。中年女はずっと“あの”調子だった」
「そうなのか?」
晩酌の用意をする手を止め、振り返るとサキチは窓の傍へと歩いていた。後ろから見ると、まるで泥を掴んでから丸めた巨大な月見団子だ。
「お前の思うのはキネマのようなシーンだろう?」
「……悪いか?」
「悪くはないがな」
窓際に腰を落ち着け、そこから見えるらしい月を見上げて尻尾を一振り。
語って聞かせるつもりはないという意思表示だろう。それなのに強いて事の詳細を、人の死に別れの話を好奇心から聞き出そうというのは下世話なことか。知りたいと思う気持ちを吐息でごまかすと、それに応えるようにサキチの尻尾が再び振られた。思わず苦笑いが浮かんでしまう。
俺は冷蔵庫から日本酒の小瓶を取り出し……テーブルにサキチを呼ぼうかと思ったけれど、やめた。盆に小瓶とお猪口を一つ載せ、そこに加えてレンジで温めなおした酒肴を中皿で二つ。どちらの皿も盛られた品は同じ。ただ、作り方を変えてある。
盆を持ち、俺はテーブルを素通りして窓際に向かった。
そんなに月が綺麗なら、月を見ながらがいいだろう。
「煮っ転がしか」
脇に置かれた盆を見て、サキチはヒゲをそよがせた。
「ああ。言われた通りの間違いなく旬のものだからな。連日は嫌だ、飽きる、とか文句言われても受け付けないぞ」
「言わんよ。時期外れではあるが、月夜には良い風情だろう」
「風情? 何で?」
「何だ? 知らぬのか」
「何だよその言い草は。月夜に里芋の煮っ転がしの何が風情なんだ?」
「ああ面倒臭い。『芋名月』でググって悟れ」
「ググ――っ?」
よもやの用語が妖怪の口から飛び出て、思わず目が丸くなる。
サキチは俺からつまらなそうに顔を背けると床に置かれた盆の上、二つの皿を見比べて言った。
「片方は、つい最近見た覚えがあるな」
「せっかくレシピを教わったからな。つっても目分量だから何となくだけど、まぁうまく出来たよ」
「ほう、あの適当なものをよくも再現したものだ。やるではないか、ヨシユキにしては」
……本当に……この化け猫は……生意気と言うかふてぶてしいと言うかこんチクショウめ。もっと素直に褒められないのか。
「一方、こちらは初めて見る」
「うちのだよ。母さんに電話で聞いて、作ってみた。ちょっと甘い味付けだから酒に合うかわからないけどな」
「合うだろうさ」
「……ん?」
サキチは、爪を一本伸ばしておばちゃんのレシピで作った色の濃い里芋を取り、ゆっくりと味わうように腹に収めた。歳経た吐息が一つ、連れ合いを探す秋虫の声に重なる。
「中年女の連れ合いは、お前の作った“家庭の味”を『うまい』と言っていたよ」
「……おばちゃん、喜んでたか?」
「泣いていた」
「……そっか」
それなら、あのおばちゃんは、後ろ髪を引かれながらも、きっととても幸せな気分で成仏したのだろう。
それならば、俺も嬉しい。
あっという間の一時の、何が何やら分からぬ間の付き合いだったけど、多少なりとも触れ合った相手がそうやって逝けたというのなら、それは本当に何よりなことだ。
「なあサキチ。あの金木犀な」
「うむ」
「生け花にするつもりじゃなくて、おばちゃんが好きだと言っていたからもらってきたんだけど……」
「そうか。では明日、現場に案内してやるよ。供えてやればいい」
現場、か。
おばちゃんがどうして死んだのか、多分、分かった。やっぱり本当はもっと詳しく――旦那さんとの会話とかも聞いてみたいけれど……やっぱり、やめておこう。
「“ひやおろし”か」
酒瓶の栓を開け、お猪口に注ぐ俺にサキチが満足そうに言う。
「これも季節物なんだろう? 一番安いやつだけど、我慢しろよ」
サキチは尻尾を一振りすると、早速酒を舐め出した。
そして、今度はうちの“おふくろの味”を食べ、何かを思うように顎を上げる。ちらりとこちらを一瞥し、
「お前の母のものはちと甘すぎるな」
「だからそう言ったじゃないか」
「ああ。しかしこれはこれで、なかなか乙だ」
「そ、そうか?」
意外なサキチの評価に驚き、自分でも驚くほどの嬉しさがこみ上げてきた。母の味を褒められるというのは存外嬉しいものだと初めて知った。
顔が変ににやけそうになるのを誤魔化そうと、我が家の煮っ転がしを一つ取って口の中に放り込む。味見の時にも思ったが、すうっと懐かしさが喉を落ちていく。
空を見上げると、歪な円を描く月が、欠けているくせに満月にも増して美しく輝いていた。
「だが――」
と、サキチが言った。
目を月からそちらへ落とすと、化け猫は牙を見せて笑っていた。
「中年女の煮っ転がしは、やはりイマイチだ」
終
091017-1102+05-1103