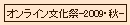楓
彼に友からの手紙が届いたのは、三日前のこと。
――奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋は悲しき――
引き記された猿丸太夫の歌の下、描かれた地図はとある背高い丘陵の中腹を指し示す。人工衛星の目が映す図と見比べれば、そこは丘に食い込む住宅地からも、張り巡らされた道路からも離れた場所、山肌を覆う雑木林の奥にあると分かる。さらに地図には小さな矢印があり、三日後、このルートを通って登っておいでと注釈があった。
友は、彼に時折こうして突飛なことを投げつけてくる。
であるから彼は慣れたもので、相分かったと電話を返し、友に「文には文を返すのが風流だよ」とたしなめられた。そのやり取りは二人の間で恒例行事となっていて、電話を切るなり二人同時に笑ったことは、二人は互いに知らねども、二人して共に相手は向こうで笑っているだろうと同時に思うのである。
そして、彼はやってきた。
川の流れる平地から、一キロをかけて緩やかに、それから急に、ぐっと空へ向けてせり上がる大地の麓に。
無論、ここは鹿の出る奥山というわけではない。猿丸太夫の胸に迫るには情緒も足りまい。エンジンの調子の悪そうな軽トラックが横を駆け抜けていった。
が、友がわざわざ歌を引いて呼びつけるからには何かあるのだろうと、彼はアスファルトで舗装された道を外れ、友が指定してきた住宅の切れ間から、生い立ち茂る林の中へと踏み入った。
夏を過ぎ、幾度かの台風も過ぎ、冬支度を始めた木々から落ちた葉が、丘の柔らかな黒肌に幾重にも。
まだ土の全てが隠されるには早いが、気をつけねば落ちた枯葉に隠れる根に足を取られそうになる。
彼は落ち葉をさり、さり、と踏みながら、友に示された場所を目指して丘を登った。
ぱり、と何か硬いものを踏み割った音がして、驚き足下を見れば――ドングリ。
気がついてみると、落ち葉の隙間に覗く土に半ば身を沈め、それとも枯葉の上に、あるいは未だ緑を留めるシダ類や草の間に、無数のドングリが散らばっていたことを知る。
そういえば、幼い頃にはよく拾って遊んだと彼は手に取った。
艶のある茶。弾丸に似た流線型の実。これはコナラだったか。あちらにある丸いものはクヌギの実だったろうか。そうだとは思うが、詳しくは忘れてしまった。
今日は小春日和。
抜けるような秋空は、木枯らし間近もまだまだ紅葉の季節と葉を残す、梢の向こうに隠れて見えない。ただ木漏れ日だけが目に刺さる。
林の中は薄暗く、初めは寒気すらしたが、しばらく歩いていると体が火照ってきた。
このままだと汗を落としそうだ。もしそうなれば、後で体が冷えてしまうだろう。彼がそう思ったちょうどその時、目の先に、ふいに、木立の切れ目が現れた。
不自然な切れ目だった。傾斜も消え、やたら平らな場所であるのも不自然だ。不自然であるのだから、けして自然の手によるものではない。そう思いながら林を抜けると、果たしてそこには人家があった。
彼は、目的地に辿り着いたのだと悟った。
人家は朽ちていた。
どういう経緯で放置され、また放置されたままになっているのかは解らないが、随分前に人の手を離れたことは、土地を囲む人の背丈より高い土壁が風化寸前にぼろくなっている様と、壁の上に覗く苔や草の生えた瓦葺きの屋根の様から判る。屋根は消された小山の傾斜がそこに移ったかのようにおかしな傾きを見せていた。
それにしても、大きな家だ。
よくもこんな所にこんな家があったものだと感心もする。
そうして彼が家を見ていると、横手から声がかかった。
「やあ、きたね」
彼の振り返った先には、友の笑顔。
「やあ、お呼ばれしたよ」
こうして会うのは、半年振りだったろうか。
しかしつい昨日にも会っていた調子で、二人は声をかけあった。
友に連れられて、今にも崩れそうな門を通り庭に案内されたところで、彼は息を飲んだ。
屋根を傾かせた家はまさに廃屋で、窓ガラスも窓枠もなくなった四角い穴から見える内は意外にもすっきりとはしていたが、やはり床や土と化した畳の所々には草が生え、かつては名士が住んでいたのであろう邸宅の面影があるからこそ侘しさつのるものだった。
それだけでも一種の趣は十分にあり、友が猿丸太夫の歌を引いてきたことにも納得しかけていた彼は、しかし友が本当に見せたかったものを目にした途端、その真意を不十分に汲み取っていたことを知り……そして、呼吸の一切を忘れてしまっていた。
そこには立派な家屋に負けじと、広い庭があった。
平らに均された庭、草一本生えぬ黒土の上、そこに、ただ一本の楓があった。
なんと鮮やかな、ああ、なんと鮮やかな紅!
すなわち異質がそこにあった。
くすんだ色、暗色、色濃いが故に重苦しい色が季節を占める中、そうであるが故に際立って異彩を放つ真紅。
木が燃え上がっているかのように雄々しく、木が葉に命の全てを吸い上げとられてしまったかのように息苦しい原色。
庭の中心からはずれ、家屋に寄りながらも絶妙な距離を離して根をはるその楓は、一度枯れかけでもしたのだろうか。頼りなくうねる細い幹をそろそろと天へと伸ばし、それでもどこか慎ましやかな姿を作っている。それは確かに自然とそうなったのだと理解するまでもなく解るのに、楓は、人の手を借りず、まるで独りでに盆栽の趣向を得たかのようだ。
それが、明らかに不自然な平地の中にある。
庭の平たさは真っ平らと言ってもいいだろう。ローラーをかけた、と言うほどではないが、それに近い。
整いすぎた庭。
何よりおかしいのは、家が荒れ放題なことに対し、肥沃のほどを思わせる土の匂いが漂う庭だけは草の芽一つすらなく、ひたすらに整然としていることだ。
……友は、相当に苦労したことだろう。
楓の他にもあったはずの草木は根こそぎ追いやられ、楓の他に残るものは一面のむき出しの土地。
草一本無い代わりとばかりに、見事に紅く色付いた楓の葉と外から舞い込んだ黄色や赤茶の葉がちらちらと黒地に錦を描いている。
美しかった。
ここでは空も何の妨げもなく見える。
高く高い空を見上げると、ああ、優しい青を湛える
視界の隅に家を囲む枯れ色の樹冠が見える。
今一時は枯れた姿を見せようとも、春になれば再び芽吹く木々の存在感が、敷地の外からさんざめいてくる。
それから目を落としていくとすぐに目の醒める紅が加わり、最後に、土の黒……。
朽ちかけた土壁が作る仕切りに、内と外、不自然と自然が明確に区切られ、されどその仕切りがあることで、自然も不自然も色合いも何もかもが強烈に己を主張し合いながら、それなのにどれもが穏やかに溶け合う『一』の世界がここに存在している。
異質たる楓を包み込む不自然。
その不自然を、異質ごと、さらに自然がおおらかな腕に抱く姿。
美しい。
ため息が漏れる。
何を聞かずとも判る。
これは、友がやったことだ。
「この家は……」
とにかく、それだけをようやっと口にした彼に、友は答えた。
「よく知らない。たまたま見つけたんだ」
「それじゃあ、俺たちは不法侵入者か」
「これだけ整理した分、これくらいはおまけしてくれるよ」
友はそう言って笑う。その手にはどこから取ってきたのか、丸いゴザがあった。
「ここに座って眺めると、抜群なんだ」
ゴザがぱっと宙に翻されて、ふわりと敷かれる。敷物に押しのけられた空気に乗っていくつか楓の
「お茶もあるよ」
ゴザの次は茶器一式と水筒の入った袋を手にして、友は彼をうながした。
彼は友の相変わらずの調子にうながされるまま、靴を脱ぎ、ゴザの上に座った。
陽光を吸い込んでいた土の温度が伝わってくる。
小春の陽気が体を包み、空からも地からも温もりを与えられる。
眼には美しい秋色。
落ち着いてみると、夜にはあまりに早いが、廃屋の中からか、土壁の影からか、コオロギの声が耳に届いてくる。遠くからは小さな鳥の声も聞こえてくる。それらがかえって周囲の静けさを強め、手際良く茶をたてる友の所作の音が一種の楽曲にも思える。
さあっと涼風が流れた。
さあわあさららと木々の枝葉が擦れて鳴らす風の音は、川瀬の音にも似て心地良い。
わずかに甘さを帯びた強い緑の匂いが鼻をくすぐり、それが茶の出来たことを報せてくれる。
「どうぞ」
「や、これはこれは。いただきます」
わざと他人行儀にやって、友から茶を受け取った彼は若草色をすっと啜った。口の中にだけ、春夏の息吹が広がった。
「いいところでしょ」
茶をずずと啜り、友が言う。
「ああ、いい所だ」
ここは無論、鹿の出る奥山というわけではない。
だが、猿丸太夫の胸に迫るに足る情緒はきっとある。
「しみじみ、秋だ」
彼が言って、茶を啜る。
「うん。秋だ」
茶を啜り、友が応える。
吹き戻しのように風がまた。今度は強く。
ざあわあさらざらと風の音が鳴る。
楓の葉が散り宙に舞う。
鮮やかに、艶やかに、音もなく舞う紅。
外からも木の葉が舞い込んで、黄、黄茶、柿渋、赤茶、朽葉、紅、とりどりの彩りが、流れ移ろう空に万華鏡の景色を描く。
二人は、目も魂も奪われた。
――山肌に 紅葉舞い散り 吹く風の 音聞くときぞ 秋は
終
091026-31-1103