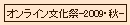落日の光に映えて
陽も傾き、西の空はまず山吹に、それからしだいに赤く赤く焼け出した。
天道が空高くにある時は、青を背に明暗対比も鮮やかに彩り豊かな錦秋も、黄昏の中では明暗対比も乏しく色褪せる。もうしばらくすれば夜の帳が『一日』の幕を下ろしにかかるだろう。すでに風は冷たさを増している。
が、友には日暮れに従い帰路に着く考えは元よりないようだった。にこりと笑い「居待ち月をここで待とう」と、廃屋の内から七輪を持ち出し今は炭を
彼は、楓を見つめ続けていた。
落日にくすむ世界に抗するがごとく、天空を焼く炎にも負けず濃い紅に燃え上がるあの楓――月明かりを頼りに眺めても、それはきっとさぞかし美しかろう。
友は燗に良い酒を持ってきたと言う。
ならば酔いを我らの間に迎えて共に宵を越え、そのまま暁天に渡って語るもいいだろう。
そして、それは、元より彼も望むところである。
「お酒は任せていいかな? 燗は君のに限るから」
彼はゴザに座ったまま肩越しに振り返り、廃屋の崩れかかった縁側にいる友へ了解を返した。
友の足下には二つの七輪がある。その一方には鍋が載り、もう一方には串に刺されたギンナンがかざされて、夏と秋の己が葉の色を詰め込んでぷっくりと丸く肥えた実が、ぼんやりと炭の炎熱に焼かれている。友の傍らには食材の盛られたザルがある。
彼はそろそろ縁側に移ろうとし、ふと、そこで思い出した。
――懐にある、その一枚。
たまにはこちらからも友へ風流を返してやろうと企み、胸に忍ばせてきた絵札。
すっかり忘れてしまっていたが……まぁ、いい。すぐ後にでも、それとも明日の朝にでも、それとももっと時を経てからでもいい。これに気づけば友も口元が綻ぶことを禁じえまい。もし友に気づかれずとも、それならばこの土地に歌を供えたこととすればいい。
彼は懐から取り出した絵札を、日没近づくにつれ色増す黒土、そこに舞い落ちた真紅の葉の上にそっと置いた。
「どうしたんだい?」
友が声をかけてくる。声にあるのは、怪訝。彼は手近な紅葉を手に取り「あしらいに良いだろう?」と応えてごまかした。それから、ゴザを持って立ち上がる。
――さて、友はいつ貴方に気づくだろうか。
彼は、背を向けたままこちらへ振り向き微笑を見せているような、歴史に歌と共に名だけを遺す偉大な歌人へと目配せし、そうして友の待つ廃屋へと足を向けた。
さわさわと大気が流れる。
さらさらと戯れるように地の上を転げた楓の葉のいくつかが、その場に残された百人一首の読み札にすっと寄り添い、落日の光に映えてしとやかに輝いた。

Illustrated by カリキモトコさん
(Copyright© かりもと)
091117-20-1121